最近、「民主主義」に興味がある。
といっても、政治活動ではなく、「民主主義」の概念や意義、成り立ちについて、ちゃんと知っておきたいと。
心理の仕事をしていると、自立支援制度や障害者手帳、障害年金、作業所などの就労支援、ヘルパーなどの生活支援といった,さまざまな福祉サービスがあることを知り、実際にそれらを利用している人たちに出会う。
日本に福祉サービスがあるのは、憲法で「健康で文化的な最低限度の生活」を保障している、基本的人権を尊重する民主主義国家だから。
あらためて「民主主義」とはなんなのかを知りたく、目に付いた本がニポン未完の民主主義。ジャーナリストの池上彰さんと、池上さんが「知の巨人」と評する佐藤優さんとの対談本。2人が語る現代日本の民主主義の危うさも読み応えがありましたが、それよりも興味を惹かれたのが、2人が「教科書」として取り上げた今回の一冊。
本書は戦後間もない1948年にGHQの指示で文部省が書き上げたもの。とはいえ、当時のアメリカの民主主義を無条件に称えたりせず、民主主義の根本精神を中高生にも理解できるように簡素なことばで、一つひとつの事柄を噛み砕いて、筋の通った文章で書かれています(社会主義についても言及していますが、よくGHQの検閲を通過できたなと思う)。
解説の内田樹さんはページ数の多さから「ほとんど学術書である」と言いながらも、本質的な洞察に満ちており、読み終えて「天を仰いで感嘆した」と絶賛しています。
それでは、「民主主義」とはなんなのか?
冒頭にはこのように書かれています。
続けて、次のように述べています。
民主主義を単なる考え方や政治体制としてではなく、実現してこそ民主主義であると強調し、家庭や職場、教育など様々な場面での民主主義のあり方を説き、各国の民主主義へと至った歴史的な経緯とともに、日本も軍が政治を掌握する以前の明治大正時代に民主主義を醸成しつつあったことを教えてくれます。
読む前から期待感がありましたが、それ以上に読み応えのある内容でした。
というより、なんで学生時代にこの本の存在を知らなかったんだろうと不思議に思いました。道徳の授業の題材としても申し分ないんじゃないかとも思ったり。
欲を言えば、「障がい者の民主主義」にも言及して欲しかった…
心理の仕事に直接関わる内容ではないけれど、福祉制度の根拠となるものについて理解を深められる一冊です。
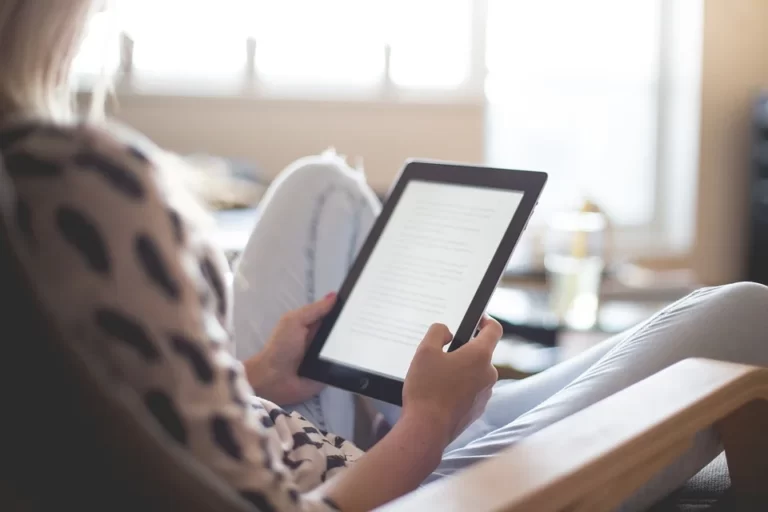



コメント